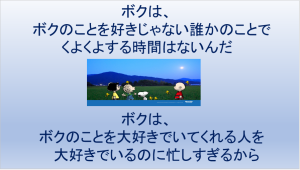一昨年、演出家の鴻上尚史さんが当時の中学校1年生に講演をされた際、「シンパシーとエンパシー」について話をされました。「シンパシー」は同情する気持ちのことで、例えば「シンデレラ」であれば「シンデレラがいじめられてかわいそうだな」という気持ち。「エンパシー」は共感する能力のことで、「シンデレラの継母はどうしてあれほどまでシンデレラに冷たく当たったのだろう」と考える能力のことだとおっしゃっていました。
当時の中学1年生のある生徒は、エンパシーの例として次のように答えました。「世間の一般的な法則からすると、誰かを仲間外れすると、仲間外れした側の結束が強まる。継母は、シンデレラをいじめることで、実の娘二人との家族の関係を強めようとした」。
これからの多様化した社会では、多様な人がいて、多様な考え方が生まれます。コミュニケーションをとることがとてもしんどい時代になるにちがいない。その時に「エンパシー」の力を持つことで、人との関係が広がるし、「自分は好きだけど、相手は嫌いかもしれない」と、自分と相手との違いを想像することにもつながると思います。
エンパシーの力を持つには、「無意識にこうだと思いこむ先入観」(アンコンシャスバイアス)を削ることが大切。「みんながやっていることは誰でもやるべきだ」とか、「赤いランドセルは女の子の物だ」という思い込みをやめてみませんか。他人に対してだけでなく、自分に対して持つアンコンもあります。「私にはこれは無理だ」とか、「私の話などどうせ聞いてくれない」とか。その思い込みから脱却するためには、「他人と違うことは間違いではない」「自分で自分の可能性を否定しない」と考えることがとても大切だと思う。
もう一つ大切なことは、人権に優しい人になりましょうよ。人権とは、人間が当たり前に生きる権利であって、もし学校の中で生徒が当たり前に生きることができないならば、学校は変わらなくてはならないし、君たち自身も変わらなくてはならないよ。
「共感する能力」を築くことがとても難しいことは、歴史の一場面から考えてもわかる。アメリカ人の多くは今なお「原爆投下は正しかった。原爆によって平和が訪れ、本土上陸作戦をやっていれば、失われていたはずの多くのアメリカ兵の命が救われたのだから意義がある」として、原爆投下は正しかったと言います。
また、シンガポールにあるワックス博物館には、焼け野原になった広島の写真と原爆のきのこ雲の写真が展示され、原爆投下を正当化する文言が綴られています。日本人にとって、原爆投下は、戦争の惨禍と非人道性を訴える象徴的な出来事ですから、こうした原爆観に驚くでしょう。でも、原爆のとらえ方で対立することなく、アメリカや東南アジアの原爆観を形成した背景を学ぶことが、「共感する能力」を育て、真の人間関係を作っていくと思う。
人間にとっての最大の罪責は罪を犯すことではありませんよ。最大の罪責は、苦しんでいる者と苦しまない、悲しんでいる者と悲しまない、という想像性の欠如。もう一つの罪責は、自分の周囲で起きている課題を自分とは関係ないと切ってしまう当事者性の欠如。広島に住んでいる20歳のアメリカ人女性は、「原爆を落とした国の人間だからこそ、原爆の悲惨さを訴えていかなくてはならない」と地道な活動を続けています。
最後に一言つけ加えれば、この想像性と当事者性を表現する唯一の手段が「言葉」であり、人の「言葉」は人生を左右するほど尊いものです。人は、「言葉」を発する前に必ず心を持っています。その心に合った「言葉」を発することで、人は人との関係を作っていきます。
その一方で、「言葉」は人を傷つける刃にもなる。その刃は、一度発してしまえば決して元に戻せない。SNSでの発信であれば永遠に残る。「言葉」は人を傷つけるだけでなく、命を奪うこともある。
「言葉」は、自分自身を表現する唯一の道具です。唯一のものならば、それは人を愛するため、癒すために使うべきだ。言葉を発する前に思慮深くあれ。